税金の滞納処分と差押さえ
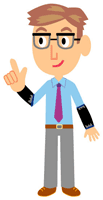 税金は法定期限までに申告・納付しないと、本来納めるべき税金とは別に、附帯税・加算税が課せられ、さらに税金を滞納していると、最悪、財産を差し押さえられることもありますので注意が必要です!
税金は法定期限までに申告・納付しないと、本来納めるべき税金とは別に、附帯税・加算税が課せられ、さらに税金を滞納していると、最悪、財産を差し押さえられることもありますので注意が必要です!それでは附帯税・加算税にはどのようなものがあるのでしょうか?
| 延滞税(附帯税) | |
|
|
|
 税金の一部、または全部を滞納、納付期限までに納税しないと「延滞税」が課せられます。
税金の一部、または全部を滞納、納付期限までに納税しないと「延滞税」が課せられます。延滞税は原則的に、納付期限の翌日から完納された日までの日数に応じて以下の通りの年率が適用されます。
・納期限の翌日から~2ヵ月後まで:「7.3%(平成28年中)」
・納期限から2ヶ月超~:「14.6%」
例えば未納所得税100万円で、法定納期限の翌日から完納までの日数が6ヶ月(180日)だった場合・・・
・100万円(未納税額)×14.6%(年率)×180(法定期限の翌日から完納までの日数)÷365=72,000円(延滞税)
となり、72,000円を100万円にプラスして納付しなければならないのです!
| 利子税(附帯税) | |
|
|
|
税金を滞納した場合でも、以下に該当する場合は延納日数に応じて延滞税ではなく「利子税」が課せられます。
・法人税で申告書の提出期限の延長が認められた場合
・届出により所得税や相続税等の延納が認められた場合
・災害等によって申告書の提出期限を延長する場合
・延納税額×利子税の年率(平成28年は年1.8%)×延納日数÷365=利子税
| 過少申告加算税(加算税) | |
|
|
|
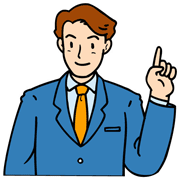 納期限内に税金を納めたが、税務調査などによって税務署から過少申告(納めた税額が少なかったこと)を指摘されて修正申告、または更正処分を受けたときに課されるのが「過少申告加算税」です。
納期限内に税金を納めたが、税務調査などによって税務署から過少申告(納めた税額が少なかったこと)を指摘されて修正申告、または更正処分を受けたときに課されるのが「過少申告加算税」です。ただし税務調査などがなく 納税者自身が過少申告に気付き、自主的に修正申告したときには過少申告加算税は課せられません。
過少申告加算税は以下のように計算されます。
・「追加納付税額(増加した税額)×10%=過少申告加算税」
また追加納付税額が期限内申告税額(当初納付した税額)、または50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分については15%が課せられます。
| 無申告加算税(加算税) | |
|
|
|
 正当な理由なく申告期限内に申告書を提出しなかったため(申告期限後に自主的に申告書を提出した場合を含む)決定処分を受けたときに課されるのが、「無申告加算税」です(申告期限内に提出しなかった場合でも、正当な理由があると認められる場合は課税されません)。
正当な理由なく申告期限内に申告書を提出しなかったため(申告期限後に自主的に申告書を提出した場合を含む)決定処分を受けたときに課されるのが、「無申告加算税」です(申告期限内に提出しなかった場合でも、正当な理由があると認められる場合は課税されません)。無申告加算税には以下の通りの税率が課せられます。
■更正等を予知してなされた場合(税務調査を受けたなど)
・納付税額が50万円以下:「納付税額×15%」
・納付税額が50万円超:「納付税額×20%」
■更正等を予知せず期限後に申告した場合(税務調査などを受けず自主的に期限後、申告した場合)
・「納付税額×5%」
| 不納付加算税(加算税) | |
|
|
|
正当な理由なく源泉徴収等により納付すべき税額(国税)を納期限までに納付しなかったときに課せられるのが、「不納付加算税」です。
不納付加算税には以下の通りの税率が課せられます。
■更正等を予知してなされた場合(税務調査を受けたなど)
・「不納付税額×10%」
■更正等を予知せず期限後に申告した場合(税務調査などを受けず自主的に納付した場合)
・「不納付税額×5%」
| 重加算税(加算税) | |
|
|
|
 過少申告加算税、不納付加算税、無申告加算税が課される場合、納税者が自主的に修正申告しなければなりませんが、その事実を隠蔽(売り上げの一部を隠すなどの行為)、または仮装(架空仕入れなどによって税務署を欺く行為)して申告した場合に、過少申告加算税、不納付加算税、無申告加算税に代えて課せられるのが、「重加算税」です(併課されるわけではありません)。
過少申告加算税、不納付加算税、無申告加算税が課される場合、納税者が自主的に修正申告しなければなりませんが、その事実を隠蔽(売り上げの一部を隠すなどの行為)、または仮装(架空仕入れなどによって税務署を欺く行為)して申告した場合に、過少申告加算税、不納付加算税、無申告加算税に代えて課せられるのが、「重加算税」です(併課されるわけではありません)。重加算税には以下の通りの税率が課せられます。
■更正等を予知してなされた場合(税務調査を受けたなど)
・過少申告加算税、不納付加算税の隠蔽、仮装:「追加納付税額(源泉徴収して納付すべき税額)×35%」
・無申告加算税の隠蔽、仮装:「追加納付税額×40%」
| 税金を滞納すると財産が差し押さえられます! | |
|
|
|
 税金を滞納すると上記のような「附帯税・加算税」が課せられますが、さらに悪質な場合、財産を差押えられることもあるのです!
税金を滞納すると上記のような「附帯税・加算税」が課せられますが、さらに悪質な場合、財産を差押えられることもあるのです!通常、正当な理由なく(病気療養中・災害にあった場合などは除く)法定納期限から50日以内(地方税は20日以内)に税金を納付しない場合、税務署(都道府県・市区町村)から督促状が送付されてきますが、この督促状が発送された日から10日以内に納税者が自主的に完納しない場合、税務署(都道府県・市区町村)は滞納者の財産を差し押さえることが出来るようになるのです!(これらの一連の流れを滞納処分といいます)
~差し押さえの対象となる財産~
・現金

・給料
・不動産(土地、建物)
・預貯金
・売掛金等の債権
・動産(車・テレビなど)
・有価証券(株券など)
・電話加入権
・生命保険、損害保険
など・・・
財産を差押さえられると、納税者はそれらの財産を勝手に処分できなくなるばかりか、差し押え後、なお納付しない場合、税務署によって差押さえられた財産が公売等の換価手続きが行われ(最近ではネットオークションを利用したインターネット公売も行われていますね)、換価された代金が滞納した国税に充当されます(差押さえ財産が債権の場合、税務署が債務者に直接、取立てを行い回収し、回収された債権は滞納した国税に充当されます)。
 しかし実際には、督促状が発送された日から10日経過後にいきなり差押さえられるのではなく、まずは訪問、電話などで何度か督促され、この督促を無視し続けたり、納付する気がないと思われると強制的に差押さえられることが多いので、もしも一括で納付できない場合でも、税務署(都道府県・市区町村)などに相談し、どのようにして納付していけばよいかを話し合えば、差押さえを免れることが出来ると思いますよ(問題は税金を納付しないことではなく、連絡しないことなのです)。
しかし実際には、督促状が発送された日から10日経過後にいきなり差押さえられるのではなく、まずは訪問、電話などで何度か督促され、この督促を無視し続けたり、納付する気がないと思われると強制的に差押さえられることが多いので、もしも一括で納付できない場合でも、税務署(都道府県・市区町村)などに相談し、どのようにして納付していけばよいかを話し合えば、差押さえを免れることが出来ると思いますよ(問題は税金を納付しないことではなく、連絡しないことなのです)。※差押さえ財産が不動産(土地、建物)の場合、その不動産に住むことは出来ますが、勝手に処分することが出来なくなります。
※税金滞納による財産の差押さえや、滞納者の財産調査などについては裁判所の許可は不要なので、差し押さえ前に裁判所、税務署(都道府県・市区町村)から連絡が来ることなく、ある日、突然、差押えられますので注意しましょう!(差押え前に文書にて通知してくれる市区町村もありますが、それは市区町村が任意でしているだけなので、基本的には文書などで通知されることなく差押えられます)
※あくまでも差押えられるのは滞納者個人の財産なので、家族の財産が差押えられるわけではありません。
※滞納者に財産がない場合、または滞納処分が執行されることによって、滞納者の事業継続や生活を維持することが著しく困難だと認められる場合には、滞納処分の停止をすることもできます。


 税金を滞納すると、最悪、滞納処分を受け財産を差押えられる可能性がありますが、滞納している税金は納期限、差し押え、または最後に督促状を受け取ってから5年(脱税の場合は7年)経過すれば時効(消滅時効)となり、時効後、税務署(都道府県・市区町村)は、権利を行使して滞納税を徴収することが出来なくなるのです(差押え、督促などは時効中断事由に該当し、その中断事由が終了した翌日から再び時効に向けてのカウントが始まりますので、実際には納期限から5年で時効になることはありません)。
税金を滞納すると、最悪、滞納処分を受け財産を差押えられる可能性がありますが、滞納している税金は納期限、差し押え、または最後に督促状を受け取ってから5年(脱税の場合は7年)経過すれば時効(消滅時効)となり、時効後、税務署(都道府県・市区町村)は、権利を行使して滞納税を徴収することが出来なくなるのです(差押え、督促などは時効中断事由に該当し、その中断事由が終了した翌日から再び時効に向けてのカウントが始まりますので、実際には納期限から5年で時効になることはありません)。
 「税金の時効」と聞くと得したように聞こえますが、税金を滞納していると国、銀行からの融資が受けられなくなったり(過去の納税状況を調査されます)、「附帯税・加算税」などが課せられます。
「税金の時効」と聞くと得したように聞こえますが、税金を滞納していると国、銀行からの融資が受けられなくなったり(過去の納税状況を調査されます)、「附帯税・加算税」などが課せられます。