個人事業税
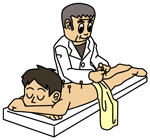
個人事業税とは、2種類ある事業税のうち、個人に課税される「地方税・直接税」のことで、法人に課税されるものは「法人事業税」となります。
-個人事業税の税率-
| 個人事業税の税率 | |
| 事業区分 | 税率(%) |
| 第一種事業(物品販売業・製造業・運送業・飲食店業・金銭貸付業など) | 5% |
| 第二種事業(畜産業・水産業・薪炭製造業など) | 4% |
| 第三種事業(税理士・弁護士・医師・司法書士・公認会計士など) | 5% |
| 第三種事業(医師・あんま・鍼灸など) | 3% |
個人事業税は上記のような税率となり、第三種事業の場合は、税率が分かれていますので注意しましょう。
-個人事業税の税額計算方法-
個人事業税の税額は、個人住民税と同じく、前年の事業所得を課税標準として計算することとなります。
また個人事業税には、「事業主控除:290万円」がありますので、具体的には以下の計算式で個人事業税を算出することとなります。
「(前年の事業所得(前年の収入-必要経費等)-事業主控除:290万円)×税率=個人事業税」
具体的には、「前年の事業所得:500万円/弁護士」の場合・・・
「(500-290)×5%=105,000円」
となります。
「事業所得」の計算方法は・・・「⇒事業所得」を参照してください(個人事業税の税額を算出する場合は、青色申告特別控除は適用外となりますので注意しましょう)。
※前年の事業所得が290万円以下であれば、「個人事業税はゼロ円」となります。
※年の途中で開業した場合は、事業主控除は290万円を月割りで計算した額となります。
-個人事業税の申告と納付-
個人事業税の場合、申告書の提出は「3月15日」が申告期限となりますが、所得税の確定申告をした場合は、個人事業税の申告は必要ありません。
また個人事業税の納付は原則、「8月/11月」の2回に分けて納付することとなっています(納付通知書が送付されてきます)。


 総合課税とは、10種類ある所得のうち(税法上は9種類)、他の所得と合計して、その合計額に対して、「
総合課税とは、10種類ある所得のうち(税法上は9種類)、他の所得と合計して、その合計額に対して、「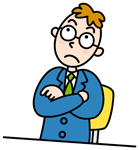 分離課税とは、その所得にかかる税金を他の所得と合計して計算せず、その所得単独で、分離して計算する課税方法で、分離課税はさらに「
分離課税とは、その所得にかかる税金を他の所得と合計して計算せず、その所得単独で、分離して計算する課税方法で、分離課税はさらに「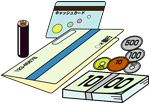 源泉分離課税とは、2種類ある
源泉分離課税とは、2種類ある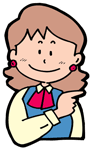
 累進課税方式とは、課税所得額が大きいほど、より税率も高くなる課税方式のことで、日本では「
累進課税方式とは、課税所得額が大きいほど、より税率も高くなる課税方式のことで、日本では「 源泉徴収とは、事業者(会社)などがあらかじめサラリーマンやアルバイト、パートの給料から、一定の税金(
源泉徴収とは、事業者(会社)などがあらかじめサラリーマンやアルバイト、パートの給料から、一定の税金( 年末調整とは、
年末調整とは、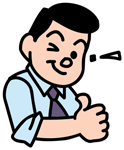 申告納税方式とは、原則として、納税者が税法に従って税額を計算し、申告することで納税額が確定する納税方式のことです(⇔
申告納税方式とは、原則として、納税者が税法に従って税額を計算し、申告することで納税額が確定する納税方式のことです(⇔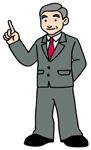 賦課課税方式とは、納税者の申告ではなく、「国・地方自治体(地方公共団体)」などが税額を確定する課税方式のことで、納税義務者に納付する税額が記載された「賦課決定通知書」が送付され、記載された税額を納めることとなります(⇔
賦課課税方式とは、納税者の申告ではなく、「国・地方自治体(地方公共団体)」などが税額を確定する課税方式のことで、納税義務者に納付する税額が記載された「賦課決定通知書」が送付され、記載された税額を納めることとなります(⇔ 損益通算とは、複数の所得がある場合に、利益があった所得(黒字)と損失があった所得(赤字)を一定の順序に従って差し引き計算し、納付することができることです。
損益通算とは、複数の所得がある場合に、利益があった所得(黒字)と損失があった所得(赤字)を一定の順序に従って差し引き計算し、納付することができることです。 老年者とは、「12月31日時点で65歳以上」の人で、なおかつ、その年(1月1日~12月31日)の「年間総所得金額が1,000万円以下」の人のことす。
老年者とは、「12月31日時点で65歳以上」の人で、なおかつ、その年(1月1日~12月31日)の「年間総所得金額が1,000万円以下」の人のことす。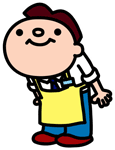 収益事業とは、公益法人等(NPO法人・宗教法人等)が以下の33種類のいずれかに該当する事業を行い(付随して営まれるものを含む)、かつ、「継続的・事業場を設けて事業を行っている」ことで、「収益事業」とみなされた場合は
収益事業とは、公益法人等(NPO法人・宗教法人等)が以下の33種類のいずれかに該当する事業を行い(付随して営まれるものを含む)、かつ、「継続的・事業場を設けて事業を行っている」ことで、「収益事業」とみなされた場合は 益金(えききん)とは、
益金(えききん)とは、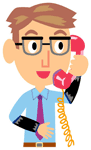 損金とは、
損金とは、 税務調整(申告調整)とは、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算された収益や費用・損失(会計上)」に、「別段の定めによる調整(加算・減算)」を行うことで、この調整によって算出された額が、「収益(会計上)⇒
税務調整(申告調整)とは、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算された収益や費用・損失(会計上)」に、「別段の定めによる調整(加算・減算)」を行うことで、この調整によって算出された額が、「収益(会計上)⇒