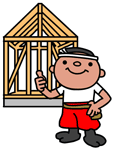 住宅ローン控除(住宅ローン減税)
住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、新築・中古の住宅(敷地)をローンで購入、または住宅を増改築(リフォーム)した場合に、一定の条件を満たせば、「
最長10年間」年末のローン残高に応じて
所得税が軽減、還付される
税額控除のことで、正式には「
住宅借入金等特別控除」といいます。
この住宅ローン控除は年々、控除額が縮小されていましたが、消費税が8%にアップしたのを機に、平成26年(2014年)4月~平成31年(2019年)6月30日まで控除額が拡大されています。
※住宅ローン控除は所得税に対して適用される制度ですが、所得税で控除しきれない場合は住民税(
道府県民税+
市町村民税)、最大97,500円まで控除の対象となります(平成26年4月~の上限は136,500円)。
| 住宅ローン減税(一般住宅の場合) |
| 入居年 |
借入金等の
年末残高の限度額 |
控除率 |
控除期間 |
最大控除額 |
| 平成21・22年 |
5,000万円 |
1.0% |
10年間 |
500万円
(50万×10年間) |
| 平成23年 |
4,000万円 |
400万円
(40万×10年間) |
| 平成24年 |
3,000万円 |
300万円
(30万×10年間) |
| 平成25年 |
2,000万円 |
200万円
(20万×10年間) |
| ~平成26年3月 |
2,000万円 |
| 平成26年4月~平成31年6月 |
4,000万円 |
400万円
(40万×10年間) |
| 住宅ローン減税(認定長期優良/低炭素住宅の特例の場合) |
| 入居年 |
借入金等の
年末残高の限度額 |
控除率 |
控除期間 |
最大控除額 |
| 平成21~23年 |
5,000万円 |
1.2% |
10年間 |
600万円
(60万×10年間) |
| 平成24年 |
4,000万円 |
1.0% |
400万円
(40万×10年間) |
| 平成25年 |
3,000万円 |
300万円
(30万×10年間) |
| ~平成26年3月 |
3,000万円 |
| 平成26年4月~平成31年6月 |
5,000万円 |
500万円
(50万×10年間) |
| 平成26年4月~平成31年6月までの非課税または税率5% |
2,000万円 |
200万円
(20万×10年間) |
-住宅ローン控除の適用条件-
住宅ローン控除の制度は、「
平成31(2019)年6月30日まで」に住宅を取得し、入居した場合に適用され、
以下の条件すべてを満たさなければ、住宅ローン控除の対象とはなりません。
・ローン残高が、上記票の限度額以内であること(例えば平成26年4月~平成31年6月までの認定長期優良住宅であれば5,000万円以内)
・ローンの対象が、住宅とその敷地に対するローンであること
・その年の合計所得金額が3,000万円(給料収入のみの場合は3,336万円)以下であること
・マイホーム取得の為の10年以上のローンであること
・次に該当する機関、団体から10年以上の借り入れであること「銀行、信用金庫、信用組合、農協、住宅金融公庫、年金資金運用基金、地方公共団体、各種公務員共済組合、勤務先からの借入で年利1%以上のもの
」
さらに・・・
◎マイホームが新築の場合
・床面積が50㎡以上かつ2分の1以上が住居用であること(居住用部分のみが住宅ローン控除の対象となります)
・工事完了の日、または取得日から6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで継続して居住していること( 震災特例法により大震災によって継続して居住することができなくなった場合でも、残りの適用期間について住宅ローン控除が受けられます)
・その他、住宅の買い替え特例等を受けていないこと(詳細は要確認)
◎マイホームが中古の場合
・床面積が50㎡以上かつ2分の1以上が住居用であること(居住用部分のみが住宅ローン控除の対象となります)
・取得日から6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで継続して居住していること
・取得した住宅が建築後に使用されているものであること
・耐火建築(マンションなど)は築後25年以内、耐火建築以外(戸建など)は築後20年以内であること
・平成17年4月1日以後に中古住宅を取得する場合は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅であること(平成25年4月1日以降に取得した場合は既存住宅売買瑕疵保険に加入していること)
・配偶者または生計を一にする親族等から取得した住宅ではないこと
・贈与された住宅ではないこと
◎増改築の場合
・自己所有で居住している住宅の増改築であること
・増改築(リフォーム)等の工事費用が100万円を超えるものであること
・工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは、居住用部分の工事費用が全部の工事費用の1/2以上であること
・増改築等を行った後の住宅の床面積が50㎡以上かつ2分の1以上が住居用であること
・増改築等の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供し、控除を受ける年の12月31日まで継続して居住していること
-住宅ローン控除の計算方法-
控除額=年末ローン残高×控除率
-住宅ローン控除を受ける場合の注意点-
原則として、この住宅ローン控除と、「居住用財産の3,000万円特別控除」は同時に受けることができません。
しかし、住宅を2人が共同所得する場合、一方が3,000万円特別控除を受けて、もう一方がこの住宅ローン控除を受けてローンを組むことは可能となっています。
また住宅ローンの借り換えや繰り上げ返済を行った場合、例えば借り換えを行い、返済期間が10年未満になった場合などは住宅ローン控除の適用外となってしまうので注意しましょう。
 所得控除とは、一定の条件を満たした場合に(基礎控除は無条件)、所得額から一定の金額を控除、差引くことができる制度のことで、所得控除額が大きいほど課税所得(課税対象額)が少なくなりますので、その結果、税額も少なくなるのです(⇔税額控除)。
所得控除とは、一定の条件を満たした場合に(基礎控除は無条件)、所得額から一定の金額を控除、差引くことができる制度のことで、所得控除額が大きいほど課税所得(課税対象額)が少なくなりますので、その結果、税額も少なくなるのです(⇔税額控除)。

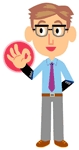 税額控除とは、一定の条件を満たす場合に、税額(課税所得×税率で算出された税額)から、直接一定の金額を控除、差引くことができる制度のことで、私たちにもっとも身近な税額控除は「住宅ローン控除」です(⇔
税額控除とは、一定の条件を満たす場合に、税額(課税所得×税率で算出された税額)から、直接一定の金額を控除、差引くことができる制度のことで、私たちにもっとも身近な税額控除は「住宅ローン控除」です(⇔
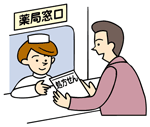 医療費控除とは、「1月1日~12月31日」までの間に支払った医療費が「10万円超える」場合、または、「総所得の5%(総所得金額200万円未満の人)を超える」場合、「最高200万円」まで税金の還付、軽減が受けられる
医療費控除とは、「1月1日~12月31日」までの間に支払った医療費が「10万円超える」場合、または、「総所得の5%(総所得金額200万円未満の人)を超える」場合、「最高200万円」まで税金の還付、軽減が受けられる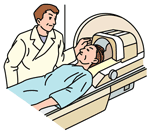 健康診断や人間ドッグを受けて、病気などが見つからなかった場合は、それらの費用は医療費控除の対象とはなりませんが、もしも健康診断や人間ドッグで病気などが見つかった場合、その治療に要する費用は、医療費控除の対象となることはもちろん、基本的には医療費控除の対象とはならない「健康診断や人間ドッグ」の費用も医療費控除の対象となるのです。
健康診断や人間ドッグを受けて、病気などが見つからなかった場合は、それらの費用は医療費控除の対象とはなりませんが、もしも健康診断や人間ドッグで病気などが見つかった場合、その治療に要する費用は、医療費控除の対象となることはもちろん、基本的には医療費控除の対象とはならない「健康診断や人間ドッグ」の費用も医療費控除の対象となるのです。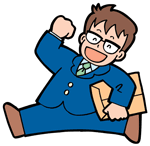
 生命保険料控除とは、「1月1日~12月31日」までの間に生命保険料(掛け金)を支払った場合に、その保険料に応じて
生命保険料控除とは、「1月1日~12月31日」までの間に生命保険料(掛け金)を支払った場合に、その保険料に応じて 損害保険料控除とは、「1月1日~12月31日」までの間に損害保険料(火災保険・傷害保険・医療保険など)を支払った場合に、支払った保険料に応じて「
損害保険料控除とは、「1月1日~12月31日」までの間に損害保険料(火災保険・傷害保険・医療保険など)を支払った場合に、支払った保険料に応じて「 地震保険料控除とは、「
地震保険料控除とは、「 公的年金控除とは、
公的年金控除とは、
 配偶者控除とは、納税者と生計を共にする配偶者に所得がない場合、または所得があっても一定金額以下(38万円以下)の場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。
配偶者控除とは、納税者と生計を共にする配偶者に所得がない場合、または所得があっても一定金額以下(38万円以下)の場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。 配偶者特別控除とは、
配偶者特別控除とは、 寡婦控除(かふこうじょ)とは、「夫と死別・離婚後まだ再婚していない・夫の生死が明らかでない」人で、扶養親族、または生計を共にする扶養親族でない子供がいる場合、かつ所得金額が500万円以下の場合などに、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「
寡婦控除(かふこうじょ)とは、「夫と死別・離婚後まだ再婚していない・夫の生死が明らかでない」人で、扶養親族、または生計を共にする扶養親族でない子供がいる場合、かつ所得金額が500万円以下の場合などに、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「 寡夫控除(かふこうじょ)とは、「妻と死別・離婚後まだ再婚していない・妻の生死が明らかでない」人で、「年間総所得金額が38万円以下の生計を共にする子供(他の扶養親族、または控除対象配偶者になっていない子供)」がいて、かつ納税者の年間総所得金額が500万円以下の場合、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「
寡夫控除(かふこうじょ)とは、「妻と死別・離婚後まだ再婚していない・妻の生死が明らかでない」人で、「年間総所得金額が38万円以下の生計を共にする子供(他の扶養親族、または控除対象配偶者になっていない子供)」がいて、かつ納税者の年間総所得金額が500万円以下の場合、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「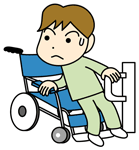
 勤労学生控除とは、勤労学生に該当する場合に、所得額が一定金額以下であれば、一定の金額、「一律、所得税27万円・住民税26万円」を所得額から控除、差し引くことができる「
勤労学生控除とは、勤労学生に該当する場合に、所得額が一定金額以下であれば、一定の金額、「一律、所得税27万円・住民税26万円」を所得額から控除、差し引くことができる「 小規模企業共済等掛金控除とは、「小規模企業共済」などの掛け金を支払った場合に、基本的に、「支払った掛け金全額」を所得額から控除、差し引くことができる「
小規模企業共済等掛金控除とは、「小規模企業共済」などの掛け金を支払った場合に、基本的に、「支払った掛け金全額」を所得額から控除、差し引くことができる「
 雑損控除とは、「災害・犯罪(盗難・横領)」などによって、資産に損害を受けた場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「
雑損控除とは、「災害・犯罪(盗難・横領)」などによって、資産に損害を受けた場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「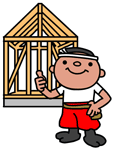 住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、新築・中古の住宅(敷地)をローンで購入、または住宅を増改築(リフォーム)した場合に、一定の条件を満たせば、「最長10年間」年末のローン残高に応じて
住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、新築・中古の住宅(敷地)をローンで購入、または住宅を増改築(リフォーム)した場合に、一定の条件を満たせば、「最長10年間」年末のローン残高に応じて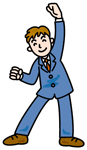 配当控除とは、株主が配当金を受け取った際に、
配当控除とは、株主が配当金を受け取った際に、 外国税額控除とは、日本に居住している者や内国法人が、外国で課税される対象となる所得や、外国で納付した場合に、一定額が
外国税額控除とは、日本に居住している者や内国法人が、外国で課税される対象となる所得や、外国で納付した場合に、一定額が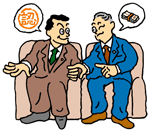 政党等寄付金特別控除とは、「政党・政治資金団体」に対する寄付を行った場合に、直接、税額の控除が受けられる
政党等寄付金特別控除とは、「政党・政治資金団体」に対する寄付を行った場合に、直接、税額の控除が受けられる